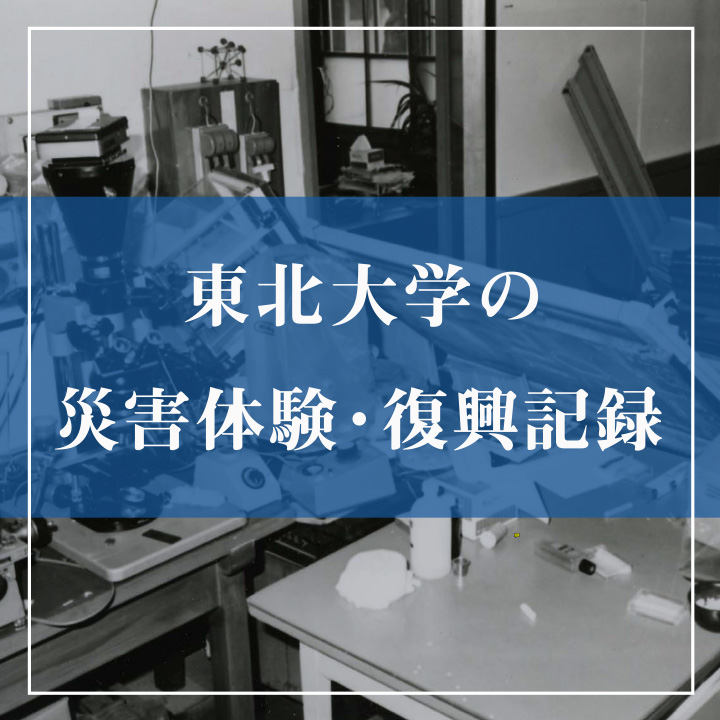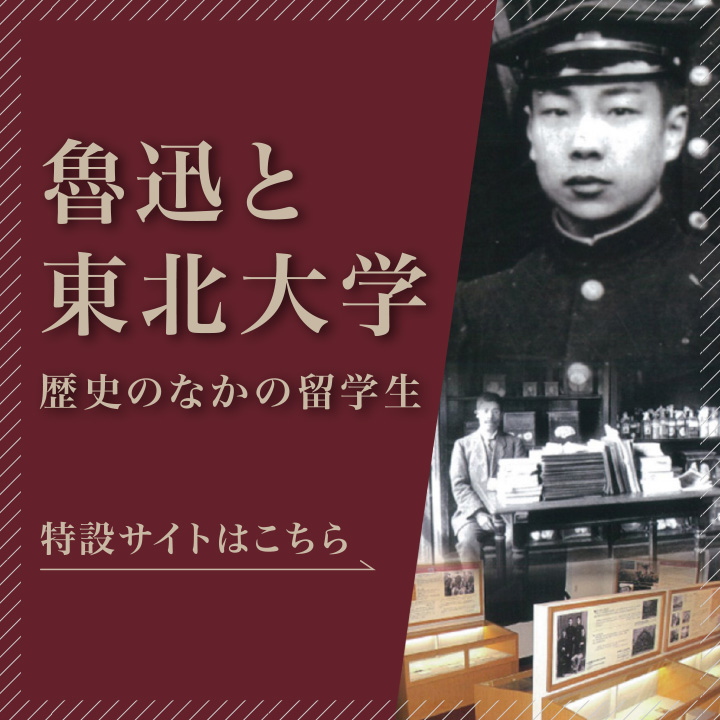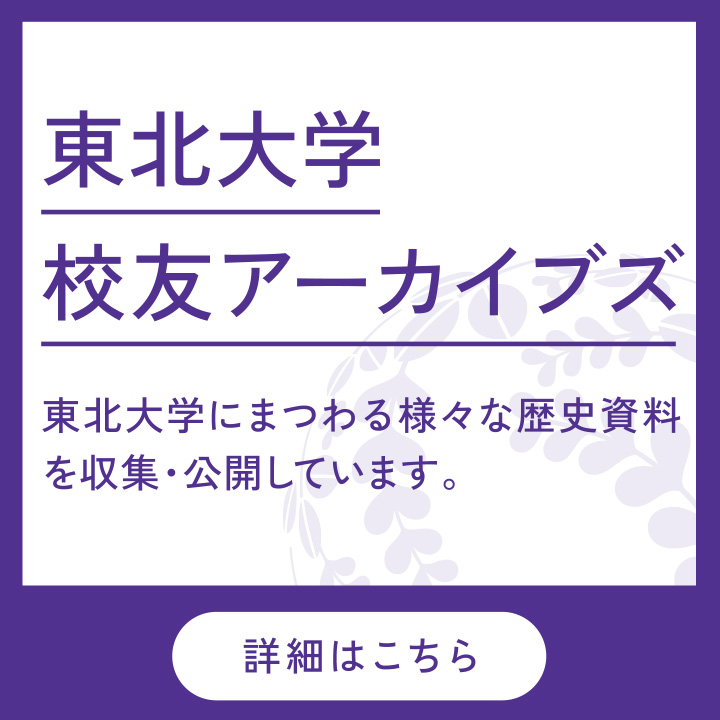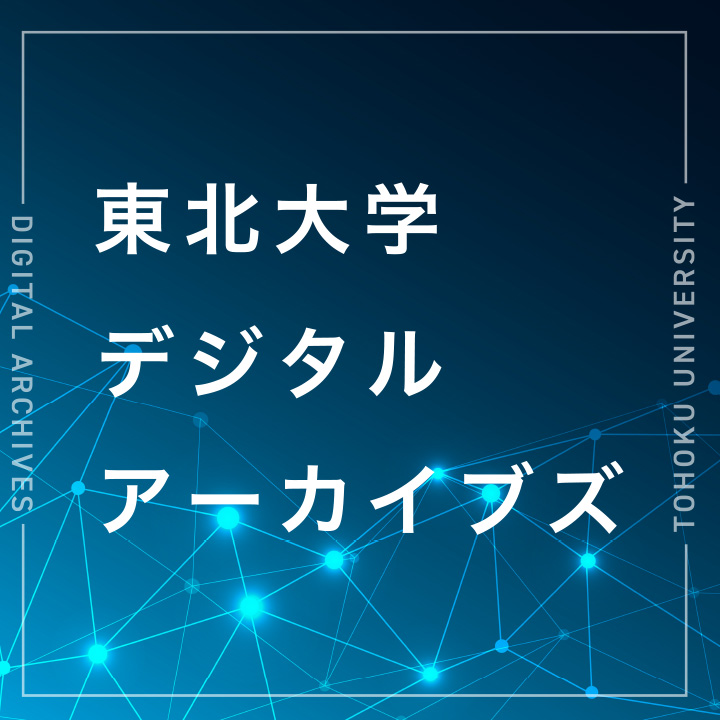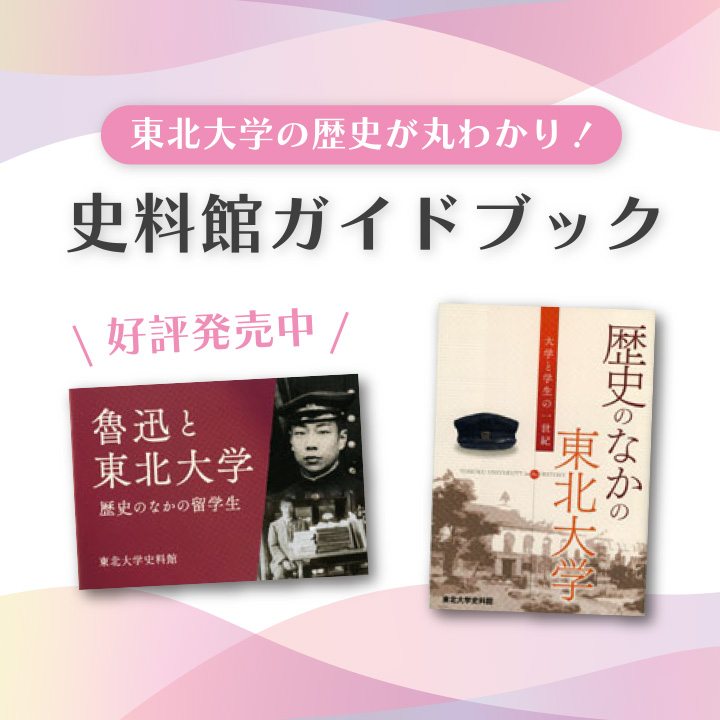未来へ、繋ぐ。
東北大学史料館は、歴史的公文書をはじめとする、東北大学の歴史に関する資料を受け入れ保存し、
これを現代および未来の人びとに伝えていく、東北大学の「大学アーカイブス」です。
NEWSお知らせ
-
2024/04/04ニュース
-
2024/04/01ニュース
-
2024/02/07イベント
-
2024/02/07イベント
-
2023/12/27ニュース
-
2023/11/11受賞
-
2023/10/05ニュース
-
2023/08/10ニュース
-
2023/06/23ニュース
-
2023/05/19採用情報
-
2023/05/18イベント
-
2022/12/27ニュース
SNS公式Xアカウント
Tweets by T_U_ArchivesCALENDARカレンダー
| S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Regular holiday
休館日
開館日
開館日
月曜日~金曜日
(祝日、夏期休業日、年末年始除く)
開館時間 10:00~17:00(最終入館は16:45まで)